心揺さぶられた「アラーキー全集」
祖父が撮った「戦前の青森」を見て写真の道へ
始まりは、秋田大学1年生の時に本屋で見た写真集だった。アラーキーこと、荒木経惟の作品群を20巻にまとめた全集。風景のスナップや女性、死などをテーマにした写真に釘付けになり、「ヌードを撮っている写真家」というイメージが激変した。中でも、妻・陽子を撮影した写真の奥には、言い知れぬものを感じた。「なんだろう、この揺さぶられる感じは?」。その感覚を確かめたくて、3年生で写真部へ。
一眼レフが欲しいー。実家の父に聞くと、祖父が使っていたヤシカのレンジファインダーカメラがあるという。使ってみて驚いた。「古いカメラなのに、こんなにディテールが綺麗に見えるんだ!」。ほどなく、祖父の荷物を片付けた際に古いガラスのネガや大量のフィルムが見つかった。プリントすると、青森市の柳町通りで薬屋を営んでいた祖父が見ていた戦前のねぶたや青森市内の町並みが現れた。「おじいちゃんは、私に写真の道を示しているに違いない!」。思い込んだらまっしぐら。夏休みの間、大学の暗室にこもって祖父が残した大量のフィルムをベタ焼きしながら、写真の道に進む気持ちが固まっていった。
「好ぎだごと、見つけてやれ」と応援してくれる両親は、大学卒業後、横浜市の東京綜合写真専門学校へ進むことに反対はしなかったが、資金援助はゼロ。バイトと奨学金で“極貧生活”に耐えた。でも、作家指向の人が多い夜間学校は刺激的だった。上野、浅草、渋谷の人混みに紛れ込み、50ミリの標準レンズで毎週何十本分もシャッターを切り、アパートの風呂場で現像、プリントしたモノクロ写真を講評し合った。
木村伊兵衛賞をとった大西みつぐ先生の指導は、シンプルだった。「狙った構図で“上手く”撮るのではなく、ストリートスナップを撮りながら人の中に入り、躊躇することなくカメラを構えて、空気のようにシャッターを切ることを体にしみ込ませる」。2年の間に写真家としての基本をたたき込まれる中で、いい写真とは何かを模索し続けた。「見る側が想像する余地のある写真こそ、人を引きつける」。そう確信し、表現に軸を置く写真家としての視点に目覚めていった。
- 仕事用とは別に、自分の作品を撮る時にはハッセルブラッドを愛用している
- 祖父が使っていたヤシカのレンジファインダーカメラは、大切な宝物
キッチンスタジオで知った
「リアルを切り取る」現場の奥深さ
写真学校卒業後は写真家を目指したかったが、背に腹は代えられず、都内のキッチンスタジオにスタジオマンとして就職した。カメラを持つ機会はあまりなかったが、撮影の様子を見ながら給料を得られる仕事はありがたく、スタジオを気持ち良く使ってもらえるよう、掃除や機材のセッティング、時には皿洗いなど、とにかく一生懸命働いた。
料理の撮影は繊細なうえに、スピードが求められる。雑誌や書籍のテーマに沿って、食材の色や形が刻々と変わる過程をベストタイミングで、そしてインパクトのある絵柄で説明しなければならない。そのために、スタッフ全員が限られた時間でコミュニケーションを取りながら、求められる動きを的確にこなすことで、料理の香りや温度、美味しさまでも写真に閉じこめていく。
「“スタジオさん”もどうぞ」。撮影現場で勧められて食べる料理の美味しさに感激するとともに、「人は食べないと生きられないのに、自分は食べることを大事にしていない」と気付いた。自宅でご飯を作り始めると「料理する面白さ」に引きつけられ、同時に「リアルを切り取る」現場の奥深さも知り、仕事がどんどん楽しくなった。
26歳を前に、スタジオを利用していたカメラマンの中里一暁さんに声を掛けられ、弟子入り。休みがないほど売れっ子の師匠は、年齢や肩書きに関係なく誰もが仕事しやすい空気を作る達人でもあった。「スタッフが意見を出し合える現場では、いいものが生まれる。一つの仕事が次につながるかどうかは、技術はもちろんのこと、仕事のしやすさや人の魅力次第だということも教えてもらいました」
アシスタントを4年務めた後、30歳で独立。師匠の仕事を手伝うかたちで始めた料理雑誌を皮切りに、人の縁がつながり、仕事ぶりを評価され、料理、パン、デザート、有名シェフのレシピ本、器のパンフレットなど、仕事の幅が広がっている。青森県立美術館の展示「Art and Air」「青森 EARTH 2014」などのカタログ撮影も一部担当している。
- パン、豆腐、出汁、「かあさんの味」…。料理の書籍の仕事は楽しい
- 青森県立美術館のカタログ用の撮影も担当している
頑張る同年代の力士に共感、「応援しなくちゃ!」
青森を素材に、自らの表現も追求
「好き」が高じて仕事につながったジャンルがある。相撲だ。たまたま見た深夜の大相撲ダイジェストで同年代の若者が厳しい世界で懸命に闘う姿を見て、「ああ、この人たちも頑張っている」と深く共感。県出身力士が数多くいることを知り、「応援しなくちゃ!」という気持ちがフツフツと込み上げた。所属の部屋を探して朝稽古を見学、国技館の桟敷席から500ミリの望遠レンズで闘う姿を追うようになった。
「いつか仕事で撮影できたら」。夢を抱いて、パソコンの待ち受け画面を力士の写真にしたり、冬の料理の取材で「ちゃんこもいい季節ですよね」とさりげなくアピール。その甲斐あって、知り合いの編集者から声がかかった。「大相撲を紹介する本の企画があるけど、やる?」。横綱・白鵬関へのインタビュー、当時新横綱になった日馬富士関への密着取材、朝稽古や力士の一日など、相撲界を分かりやすく紹介した「わくわく大相撲ガイド」(河出書房新社)は好評を博し、「押し出し編」「寄りきり編」と3冊を出版。これまでに撮りためた写真も使用され、顔を覚えてくれた力士も増えた。
一方で、「自分の表現」も追求し続けている。素材は、青森。実家がある青森市油川周辺の海や海小屋、雪に埋もれた赤や青のトタンの小屋の写真を見た東京の友達に、「日本じゃないみたい」と言われたからだ。自分には当たり前の風景、でも考えてみるとこっち(都会)にはない景色が青森にはあふれている。たい積する青森の不思議な魅力に気付いて以来、もう10年以上、年に数回帰省しては、地層や岩塊、雪景色、森などを撮り続けており、そのたびに「まだまだ知らない青森がある」と感じている。
撮り溜めた写真を2012、13年に東京と青森の個展で発表した。青森県立美術館での個展では「触れる」をテーマにオープンアトリエも行い、参加者にこう語りかけた。「一枚の写真には、自分が予想していなかった新しい発見が眠っています。目の前の被写体に話しかけ、観察し、深く向き合うことで被写体に“触れ”てみましょう」。10月で、独立から丸8年。ファインダー越しに見える世界のその奥をのぞき込み、感触を確かめながら、シャッターを切り続けている。
- 国技館には場所中に3回ほど通う相撲好き。とり溜めた写真は膨大な数に
- 初めて国技館に行った時には、興奮のあまり全カットが手ブレ…。その後は、「撮るため」に出かけている
- 東京での個展。濃淡が印象的な緑の世界と、ざらついた表面の感触が伝わる石の世界
- 東京での個展。にび色の空の下に、不思議な色合いの世界が広がる作品
「次は、角界でご活躍中の小野川親方(元武州山関)です。地道に努力を重ねる真面目さがステキな方です^^」(柿崎真子さん)
<2015年5月9日 インタビュー>
編集後記:「思い込み体質」で、仕事に表現にばく進する姿に脱帽
2013年6月、私の出身校である青森東高校同窓会のメーリングリストで「同窓生の写真展情報」を知って出かけた茅場町の会場で初めて、柿崎さんにお会いしました。「アオノニマス」という不思議なタイトルは、正方形の写真がマス目のように続くという意味と、青森という地で撮影している、という意味の造語とのこと。
幹を覆う苔と葉の緑が折り重なる八甲田の森、初冬の葉が落ちた広葉樹に囲まれた宇曽利湖、大小の凹凸が連なる石灰岩質の岩が造り出す海辺の造形…。その場の湿度、温度、音、感触を包括する写真群は、一連の流れを持つ写真集でこそ見てほしい世界です。ご希望の方は、柿崎さんにお問い合わせください。 →kaki@kakizaki-photo.com
- 2冊作った写真集は、「アオノニマス 雪」(左)と「アオノニマス 肺」
「思い込み体質なんです」とカラカラ笑う柿崎さん。中学で美術部、高校で演劇部に入ったものの「やっぱり違う…」と続かなかった路線に対しては、「何か、表現したかったんでしょうね」と自己分析。その表現したい思いに火をつけたおじい様の写真は、ぜひ拝見したいところ。願わくば、真子さんとの「二人展」のかたちで。
ちなみに、青森での撮影で、現場まで車で送迎してくれるお父様。最初は「何、撮ってるんだが、わがんね」と言っていたのに、「好きそうな石、あったよ」と、木造の海岸にある地層と埋没林などを事前にリサーチするまでに嗜好を理解してきたとか。息の合った親子の連係プレーで、ますます「知られざる青森」を見せてくれることでしょう。
そして、あふれる思いが止まらなかった相撲話題。相撲協会で不祥事があった時には、「一人でも客足増やさねば」といつもより多く国技館に足を運び、東奥日報の明鏡欄に「みんなで応援しましょう!」と投稿したという武勇伝も。「思い込み」を力に、常に全力で物事に向き合う柿崎さんの今後の活躍が楽しみです。(編集・小畑)
- 青森県立美術館での個展。「正方形の連なり」が独特のリズムを生み出す
- 青森県立美術館での個展。白い空間に、真っ白な雪景色が浮かび上がる


 008 柿崎真子
008 柿崎真子 












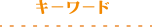
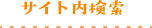
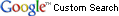

コメントを残す